仕事は忙しい。
保育園ではいつも最後にお迎え。
やっと迎えにきた母親に緊張がゆるんだのか、泣いている子ども。
そんな子どもの姿をみて
「帰るよ!さっさと準備して!!もうこんな時間なんだから!!」
と、ついついイライラしてしてしまう。
遅くなったのは自分の仕事のせいなのに、、、
お友達がみんな帰ったあとも、ひとりで保育園に残っていたのに、、、
夜眠る前、子どもの寝顔を見ながら保育園でのことを振り返れば、「なんであんなこと言ったんだろう、、、」と後悔するばかり。
子どもと「まとも」に会話をする時間もない。
思い描く「母親」とは程遠い「母親」の姿。
仕事でほとんど家にいない「母親」のことを、どんな風に思っているのだろうか。
「母親」から発せられる理不尽な言葉を、なんと感じているのだろうか。
作り笑いではなく、子どもは自分の素直な気持ちを私に語ってくれるときがくるのだろうか。
子どもの話に黙って耳を傾ける器量が、そのときには私にもできているだろうか。
今更かもしれない、、、けれど、どうにかしたい、、、
そんなお母さんの気持ちを落ち着かせるために、小説で「読活」はいかがでしょう?
小説によって心が揺さぶられることは、主人公や話の舞台に、自身の何かの投影をするからなのかもしれません。
けれども、なぜそんなに涙を流してしまうのか?を考えるだけで、心が穏やかになるものです。
心の揺れ動きを味わえるからこそ、そのあとに落ち着きが戻ってきます。
投影する力を借りて、ザワザワとした罪悪感や漠然とした不安を、このさい小説にぶつけてみてはどうかと思うのです。

たとえば、重松清さんの『きよしこ』のなかに、このような言葉があります。
「いつか ―― いつかでいい、いつか、君の話を聞かせてくれないか。
うつむいいて、ぼそぼそとした声で話せばいい。ひとの顔をまっすぐに見て話すなんて死ぬほど難しいことだと、ぼくは知っているから。
ゆっくりと話してくれればいい。君の話す最初の言葉がどんなにつっかえても、ぼくはそれを、ぼくの心の扉を叩くノックの音だと思って、君のお話が始まるのをじっとまつことにするから。
君が話したい相手の心の扉は、ときどき閉まっているかもしれない。
でも、鍵は掛かっていない。鍵を掛けられた心なんて、どこにもない。ぼくはきよしこからそう教わって、いまも、そう信じている。」
あなたが思っていること、なんでもいいから本に向かって呟いてみませんか。
後悔していること、悩んでいること、イライラした気分、なんでもいいから、本に向かって話してみるという試みです。
人に話しづらいことならいっそう、本に聞いてもらう、というわけです。
頭であれこれ思い悩むより、思っていることを口に出してみるだけで、心は穏やかになるものです。
ときには、本が悩みを解決してくれるヒントを出してくれることさえ、あります。
いかがでしょう。
このような「読活」、あなたもやってみませんか?
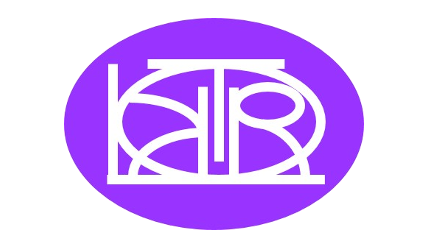










コメントを残す